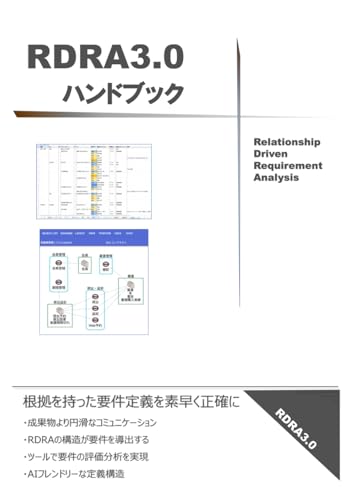シリーズ: 要件定義とはそもそも何か
- 要件定義の目的とゴールとは
- 要件定義の重要ポイント〜要望・要求・要件を見極める
- 事業・業務・システムの3階層で要件を捉える
- 業務フロー図で見える化する業務プロセスからシステム要件への道筋
- ユースケースとロバストネス図によるシステム要件定義
- システム要件定義の成果物〜設計へのインプットを作成する
- 要件定義とソフトウェアアーキテクチャ設計
- 要件定義とクラス設計
- 要件定義とデータベース設計
- 要件定義と画面設計
- 要件定義とAPI設計
- 要件定義とバッチ処理設計
- 要件とは何か
- 非機能要件とは何か
- 要件定義を学ぶ人におすすめの書籍まとめ(本記事)
- 移行要件とは何か
- 要件定義のプロセスと成果物を体系的に理解する【全体像まとめ】
TRACERYプロダクトマネージャーの haru です。
要件定義や要求に関する書籍は数多く出版されていますが、専門的で内容が難しく、読みこなすのは簡単ではありません。
そこで本記事では、私が実際に読み、要件定義の理解を深めるうえで実務にも役立つと感じた書籍を厳選して紹介します。
要件定義の入門
はじめよう!要件定義〜ビギナーからベテランまで
「要件とは何か」「要件定義とは何か」「機能とは何か」、そしてそもそも「仕事とは何か」という基本概念を平易な言葉で噛み砕き、初学者にもわかりやすく解説しています。
要件定義は業務要件定義とシステム要件定義に大別されますが*1、本書はシステム要件定義に重点を置いています。
「機能」「UI」「データ」を軸に、現場でそのまま活用できる要件定義の進め方を具体的に示しています。
入門書として位置づけられていますが、サブタイトルにある「ビギナーからベテランまで」の言葉どおり、後半の準備編・助走編・離陸編まで読み進めれば、要件定義プロセスを体系的に理解でき、経験者にとっても知識をさらに深められる一冊です。
はじめよう!プロセス設計〜要件定義その前に
前述の『はじめよう! 要件定義 ~ビギナーからベテランまで』がシステム要件定義に重点を置いているのに対し、本書は業務要件定義に主眼を置いています。
本書の業務要件定義の核心となるのは、業務プロセスの設計です。本書は、プロセス設計の具体例を示しながら理解しやすく解説しています。
本書からは「業務プロセスを組み立てるには、仕事そのものを深く理解することが不可欠である」というメッセージが伝わってきます。
中級者向け
ソフトウェア要求第3版
「第1部 ソフトウェア要求:だれが、何を、何のためにするのか」では、ソフトウェア要求を理解するための基本的な考え方を体系立てて解説しています。
特に、要求の階層構造(レベル)や種類、良い要求を作るためのプラクティス、そして要求に関して顧客が持つ権利と責任などについて、丁寧に解説しています。
「第2部 要求開発」では、「1枚の絵は1024の語に値する」という言葉の通り、要求を多角的にモデル化し図として表現する手法を詳しく解説しています。
さまざまな観点から要求を図示する具体例が紹介されており、要件を視覚的に整理したい読者にとって参考になります。
著者Karl Wiegersは2023年に新著「Software Requirements Essentials: Core Practices for Successful Business Analysis (English Edition)」も出版しており、最新の知見を求める方はそちらも合わせて読むと理解がさらに広がるでしょう。
以下の記事で取り上げられていますので、ぜひ参考にしてみてください。
要求を仕様化する技術・表現する技術 -仕様が書けていますか?
著者が提唱するUSDM(Universal Specification Describing Manner)は、要求仕様を正確に定義するための手法です。
USDMを学べば、要求や仕様を的確に表現するための具体的な手法と考え方を体系的に理解できます。
本書では、USDMによる記述方法だけでなく、要求や仕様を正しく表現することの価値や効果、さらに記述の不備が後工程の設計や実装に及ぼす悪影響を、第1部「要求仕様にまつわる問題」で書籍全体の半分を割いて詳しく解説しています。
たとえUSDMを採用しなくても、要求定義や要件定義に携わる方は、この前半部分を読むだけで要件定義で押さえるべき重要な視点と判断基準を把握できます。
だまし絵を描かないための要件定義のセオリー
要件定義をはじめとする上流工程は属人性が高く、「これをやれば正解」という定型的な手法は存在しません。
だからこそ、進め方や重視すべきポイントを自ら見極める姿勢が求められます。
本書は、著者が多くの現場で培った経験をもとに、要件定義を進めるうえで欠かせない視点と判断基準を説明しています。
「第Ⅱ部 要件定義の実践」では、実務に直結する具体的な進め方を紹介しています。
とくに「業務フロー作成時の留意点」や「4章-4 業務プロセス要件の明確化」は、業務フローを設計・改善する場面で活用できる実践的な指針となるでしょう。
ユーザのための要件定義ガイド 第2版 要件定義を成功に導く128の勘どころ

要件定義の不備がプロジェクトの失敗を招くことは珍しくありません。
IPAの「ユーザのための要件定義ガイド 第2版」は、要件定義におけるリスクを避けるために知っておきたい典型的な課題と対策をまとめています。
具体的には次のような問題が取り上げられています。
- 現行業務やシステムを十分に理解できず、正確な現状把握ができない
- ステークホルダーを見誤り、必要な要求を抽出できない
- 経営方針や事業戦略に沿った要求が反映されない
- 抽出した要求が全体として効果的かつ必要十分でない
- 要件定義に必要な期間や労力を定量的に予測できない
要件定義を始める前に一読しておけば、発生しがちなリスクを先回りして把握し、失敗を防ぐための具体的な行動指針を得られるでしょう。
要件定義手法のRDRAを学ぶ
RDRA3.0 ハンドブック:根拠を持った要件定義を素早く正確に
要件定義手法RDRAの、2025年時点の最新のガイドブックです。
RDRAは生成AIの進化に伴い、表形式で定義し、さらにスピード感を持って要件定義を進める方法に舵を切りました。
RDRAのベースとなる考え方自体はRDRA2.0から大きな変化はなく、生成AIに対応したのがRDRA3.0と考えられます。
RDRA3.0 ハンドブックを読んだ上で、RDRA自体の基本的な考え方を更に学びたい方は以下も参照してみてください。
RDRA 2.0
RDRA 1.0
最後に
本記事では、要件定義の理解と実践に役立つと私が実感した書籍を紹介しました。
基礎から応用までを幅広くカバーしたこれらの書籍は、知識を整理し体系的に深めるのに役立ちます。
ぜひ自分の役割や課題に合わせて気になる一冊を選び、日々の業務やプロジェクトで学びを実践してみてください。
読書で得た知識と現場での経験を重ねることで、要件定義に欠かせないスキルと視点を養うことができるでしょう。
次回は、移行要件とは何か、というテーマについて、説明します。



![[改訂第2版] [入門+実践]要求を仕様化する技術・表現する技術 -仕様が書けていますか? [改訂第2版] [入門+実践]要求を仕様化する技術・表現する技術 -仕様が書けていますか?](https://m.media-amazon.com/images/I/51hV6os4M5L._SL500_.jpg)